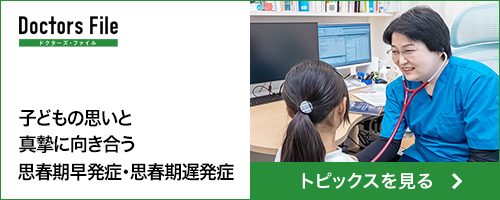睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは
睡眠時無呼吸症候群とは、眠っている間に呼吸が何度も止まったり(無呼吸)、浅くなったり(低呼吸)することを繰り返す病気です。大人の方にも多く見られますが、実は子どもにも発症することがあります。
呼吸が止まることで、体に取り込まれる酸素の量が一時的に減少し、脳が「呼吸しなさい」と指令を出すため、睡眠が途切れてしまいます。これにより、深く質の良い睡眠が妨げられ、様々な症状が現れることになります。
特に子どもの場合、体が成長途上にあるため、睡眠が妨げられることの影響は大人以上に深刻になることがあります。日中の生活だけでなく、精神面や学業にも影響が出ることがあるため、早期に気づき、適切な治療を行うことが非常に重要です。
子どもの睡眠時無呼吸症候群の原因
大人の睡眠時無呼吸症候群の主な原因が肥満であるのに対し、子どもの睡眠時無呼吸症候群の原因には、アレルギー性鼻炎、扁桃肥大が挙げられます。
その他にも、以下のような原因が考えられます
アレルギー性鼻炎
鼻づまりが慢性的にあると、口呼吸になりやすく、いびきや無呼吸の原因となることがあります。
肥満
お子さんでも肥満が進むと、首周りに脂肪がつき、気道が狭くなることがあります。
顔面や顎の発育不全
顎が小さい、歯並びが悪いなど、骨格的な問題が原因となることもあります。
神経筋疾患
まれですが、呼吸に関わる筋肉の機能が低下している場合もあります。
これらの原因によって、眠っている間の空気の通り道が狭くなり、いびきや無呼吸が引き起こされてしまいます。
子どもの睡眠時無呼吸症候群の症状
お子さんの睡眠時無呼吸症候群の症状は、夜間のものと日中のものに分けられます。
夜間の症状
| 大きないびき | 典型的な症状です。寝息が荒い、苦しそうに見えることもあります。 |
|---|---|
| 呼吸の一時的な停止 | いびきが止まり、数秒~数十秒呼吸が止まった後、大きないびきとともに呼吸が再開する様子が見られます。 |
| 寝相が悪い | 苦しくて寝返りを頻繁に打ったり、仰向けではなくうつ伏せで寝たがったりすることがあります。 |
| 寝汗が多い | 呼吸のために体力を消耗し、寝汗をかきやすくなります。 |
| 夜尿症(おねしょ) | 深い睡眠が取れないため、おねしょが続くことがあります。 |
| 就寝時の咳 | 気道が刺激されて咳が出やすくなることがあります。 |
日中の症状
| 日中の眠気、だるさ | 夜間にぐっすり眠れないため、朝起きるのが辛かったり、日中も眠そうにしていたりします。 |
|---|---|
| 集中力の低下 | 授業中に集中できなかったり、居眠りをするなど日常生活に支障をきたすことがあります。 |
| 学業成績の低下 | 集中力不足から、学習面にも影響が出ることがあります。 |
| 多動性、衝動性 | 眠気やイライラから、落ち着きがなく、衝動的な行動が増えることがあります。 |
| 成長障害 | 成長ホルモンは深い睡眠中に分泌されるため、睡眠が妨げられると身長の伸びに影響が出ることがあります。 |
| 口呼吸、アデノイド顔貌 | 慢性的な口呼吸により、顔つきが変わることがあります(上顎前突、歯列不正など)。 |
| 食欲不振 | 全身のだるさから食欲が落ちることや体重増加不良もあります。 |
これらの症状は、風邪や一時的な疲れと見過ごされがちですが、もしお子さんに複数の症状が見られるようでしたら、一度ご相談ください。
子どもの睡眠時無呼吸症候群の診断と治療方法
診断方法
問診と診察
まず、親御さんからお子さんの睡眠中の様子や日中の症状について詳しくお伺いします。
喉の奥や鼻の状態を診察し、アデノイドや扁桃腺の肥大がないかを確認します。
簡易検査
自宅で、普段と同じように寝ている間に検査を行います。
指先や鼻の下にセンサーを取り付け、睡眠中の呼吸状態や酸素飽和度などを測定します。
AHI(無呼吸低呼吸指数)と呼ばれる数値から、診断します。
治療方法
原因や重症度によって、治療方法は異なります。
当院ではお子さん一人一人の症状に合わせて治療を行うために、生活表(睡眠時間や生活リズム)を用いた評価を行っています。
薬物療法
アレルギー性鼻炎など、鼻詰まりが原因の場合は、点鼻薬や内服薬で鼻の通りを良くする治療を行います。
ステロイド薬の点鼻薬や抗アレルギー薬などが用いられます。
CPAP(シーパップ)療法
大人でよく用いられる治療法ですが、お子さんでも、手術が適用できない場合や、肥満が主な原因の場合などに検討されることがあります。
寝ている間にマスクを装着し、圧力をかけた空気を送り込むことで気道の閉塞を防ぎます。
歯科矯正治療
顎の形や歯並びが原因となっている場合は、矯正装置を用いて顎の成長を促したり、歯列を整えたりすることで、気道を広げる治療が行われることがあります。
生活習慣の改善
肥満が原因の場合は、食生活の見直しや適度な運動による減量が重要です。
また、寝る前のスマートフォンやゲームの使用を控えるなど、質の良い睡眠を促す生活習慣も大切です。
当クリニックでは、お子さんの状態を総合的に判断し、一人一人に合わせた治療や生活指導を行います。
ご自宅で気をつけること
「もしかして睡眠時無呼吸症候群かも?」と感じたら、まずはご自宅でお子さんの様子を観察してみてください。
寝ているときの音をよく聞く
眠りが浅くないか、夜中に途中で起きることはないか、普段から大きないびきをかいていないか、呼吸が止まるような瞬間がないか、注意深く耳を傾けてみましょう。
小児の場合は夜尿症やトイレで起きる場合は、実は睡眠時無呼吸症候群の原因による場合もあります。
寝顔を観察する
苦しそうに呼吸をしていないか、口を開けて寝ていないか、寝相は悪くないかなどをチェックします。
日中の様子を記録する
朝起きるのが辛そうか、日中眠そうか、集中力がないように見えるかなど、気になる症状があればメモしておきましょう。
日中起きるのがつらかったり、朝起きると喉が乾いている場合も睡眠時無呼吸症候群が原因の可能性もあります。
寝室の環境を整える
適度な室温と湿度を保ち、寝具は清潔に保ちましょう。
規則正しい生活リズム
毎日の就寝・起床時間を一定にし、質の良い睡眠を心がけましょう。
アレルギー症状のケア
もしアレルギー性鼻炎がある場合は、鼻詰まりを軽減するための対策(点鼻薬の使用、部屋の掃除など)も大切です。
このような場合はご相談ください
朝起きることができない場合は起立性調節障害ではなく睡眠時無呼吸症候群が隠れている場合もあります。また、子どもの睡眠時無呼吸症候群はときに夜尿症や成長障害を合併することもあります。当院では小児科医としての視点から総合的に診断し、お子さん一人一人に合った治療を行うことができます。
睡眠がうまく取れていないと日常生活に大きな支障をきたすため、
- いびきがひどい、睡眠中に呼吸が止まることがある
- 日中は常に眠そう、集中力が持続しない
- 夜尿症の症状がある、寝相が悪い
- 朝、すっきりと起きることができない
などの症状がありましたら一度受診を検討ください。